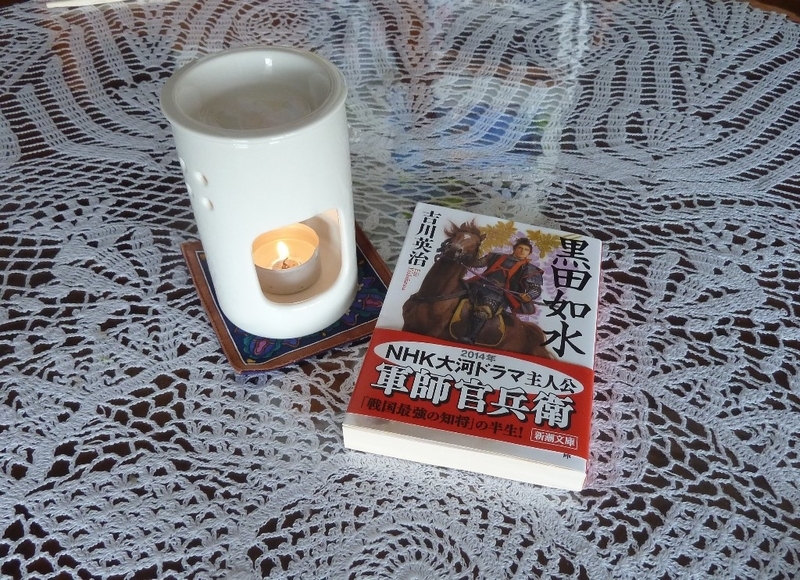
『軍師 官兵衛』を見ています。2つのドラマの共通項は
公共放送で、どこまで信仰というテーマを取り扱うのか
その辺りへの興味深さもあって、楽しんで見ています。
『八重の桜』では聖書箇所、讃美歌が思いの外、多用
されていたことに驚きました。どんな時代にあっても、
聖書の言葉は真実であること、心の琴線に触れる
讃美の調べは感謝の応答、つまり神への礼拝である
ことを確認できた気がします。
さて、ことしの『軍師 官兵衛』の見どころはいかに?
ということで歴史に疎い私は、ドラマを見る前に予習の
つもりで一冊の本を読みました。さすがに前宣伝の
大きさゆえに、書店には官兵衛関連の本がズラリ!
選びかねたので、安直ではありますが、若い頃に
読み始めると、やはり期待に違わず面白い!
ライト・ノベルに慣れ親しんでいる若い世代には、
やや硬い、難しいと思われるかもしれませんが、
流れるような文体に、いつしか引き込まれている
ことに気づくでしょう。文豪による名文を味わうのは、
実はすごく贅沢な時間ではないかと思うのです。
どうしても読書の中心がキリスト教関連の本になる
ため、独特の言い回しや専門門用語に慣れっこに
なっているところがあります。だから専門書以外で
たまに出会う名文、言い得て妙という美文に「お~!
素晴らしい」と感動を覚えることがあります。
『黒田如水』の中にもキラリと光る箇所が随所に
ありました。いくつか挙げておきます。
「怒涛の中にあっては怒涛にまかせて天命に従って
いることである。しかも断じて虚無という魔ものに引き
込まるることなく、どんな絶望を見せつけられようと
心は生命の火を見失わず、希望をかけていること
だった。いやそうしてその生命と希望をも超えて、
いよいよという最期にいたるもこれに乱されない
澄明なものにまで、天地と心身を一つのものに観じる
修行でもあった。」(p.345)
「彼がひとつの死生観をつかむには、それ以前にまず
これらの怨恨や憤怒はおよそ心の雑草に過ぎない
ものと自ら嘲笑うくらいな気持ちで抜き捨てなければ
到底、達し得ない境地なのであった。―そうした心中の
賊に打ち剋つには、あの闇々冷々たる獄中はまことに
天与の道場であった。」(p.351-352)
「ああ、ことしも秋の稔りはよいな」と、路傍の稲田の
熟れた垂り穂にうれしさを覚え、朝の陽にきらめく
五穀の露をながめては天地の恩の広大に打たれ、
心がいっぱいになるのだった」(p.353)
神さまへの感謝、賛美の辞句も通り一遍ではなく、
吟味して、よく練って、人の心に留まるようなものに
しなければと、改めて勉強になりました。